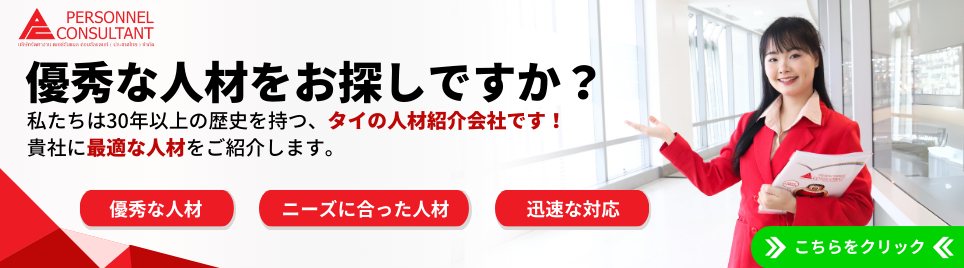2021年のクーデター以降、ミャンマー国内の大学が閉鎖や機能停止に追い込まれたことで、進学を希望する若者たちは国外に学びの場を求めるようになりました。
その中でも、地理的・文化的に近いタイは、多くのミャンマー人学生にとって現実的かつ魅力的な選択肢となっています。
実際に、2024年の第2学期には、タイの大学に在籍しているミャンマー人留学生の数は13,638人にのぼりました。【สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทายาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม】
今回は、そんなミャンマー人留学生がどのような思いでタイに渡り、どのような学生生活を送り、将来に何を見据えているのかを探るため、バンコクにある大学に通う10人にインタビューを行いました。
インタビュー対象
バンコクの国立大学に通う7名、私立大学に通う3名、計10名のミャンマー人留学生にインタビューを行いました。
男女比は半々で、学部生が7名、大学院生が3名という構成です。
専攻分野は機械工学、英語コミュニケーション学、経営学、タイ研究学、建築学、観光学など多岐にわたっており、幅広い学問領域で学んでいることがわかります。
なぜタイを選んだのか・学業への思い
ミャンマーの大学閉鎖と留学の背景
2021年2月1日、ミャンマーで国軍によるクーデターが発生し、元指導者アウンサンスーチー氏が率いる民選政権が崩壊しました。
この政治的混乱の影響は教育分野にも大きく及び、国内の大学は一時的に閉鎖され、その後も多くが再開できない状態となりました。
さらに、多くの大学教職員が市民不服従運動に参加し大量に退職したことで、教員不足が深刻化し、授業再開の見通しが立たなかったことから、ミャンマー国内での高等教育の継続は極めて困難な状況となりました。【私学高等教育研究所 アルカディア学報 パンデミックと政変後のミャンマーの教育と大学〈上〉】
2023年には、授業の再開が発表されましたが、政変後に失われた人材や一度停滞した教育を取り戻すためには、更なる時間が必要だと考えられています。
こうした状況を受けて、将来のキャリア形成を見据えた多くの若者は、学びの場を国外に求めるようになりました。
なぜタイを選んだのか
ミャンマーの学生たちが国外に学びの場を求める中で、インタビューに応じた学生たちは、タイを留学先として選んだ背景に共通する3つの理由を語ってくれました。
1. 地理的・文化的な近さ
タイはミャンマーと国境を接する、地理的に最もアクセスしやすい隣国の一つです。
何かあったときに家族がすぐに駆けつけられるという安心感は、学生本人だけでなく、家族にとっても大きな安心材料となっています。
また、仏教を中心とした価値観や食文化など、文化的な共通点が多いことから、生活への適応もしやすいという声が聞かれました。
異国での生活に不安を感じる中で、地理的・文化的に近いことは、タイを選ぶ大きな要因の一つとなっています。
2. 比較的安価な学費と生活費
オーストラリア、日本、欧米諸国と比べると、タイの学費や生活費は大幅に安価であり、経済的な負担を抑えながら留学できることが魅力とされています。
さらに、国立大学では奨学金制度も充実しており、インタビューに協力してくれた7人の国立大学生のうち4人が、大学が提供している奨学金を受給していました。
こうした経済的支援の存在は、学業継続を後押しする重要な要素となっています。
3. ビザ・入学要件の柔軟さ
タイの大学は、欧米諸国に比べてビザ取得や入学要件が比較的柔軟です。
たとえば、ある学生はオーストラリアの大学院に進学を希望していたものの、政情不安によるビザの発給拒否により断念し、最終的にタイを選択したと話してくれました。
また、私立大学の一部ではIELTSやTOEFLなどのスコア提出が不要な場合もあり、英語で基本的なコミュニケーションができれば入学できる環境が整っている点も、学生にとっては魅力的です。
タイでの生活と困難
インタビューを通じて明らかになったのは、ミャンマー人留学生の多くが文化や生活環境への適応においては大きな困難を感じていないという点です。
仏教を中心とした価値観や食文化の類似、地理的な近さなどが、生活の安定や安心感につながっていると言えます。
また、経済的な面でも、奨学金の利用や仕送り、大学院生に関してはフリーランスの仕事の給料によって、多くの学生が十分な生活をできているようでした。
一方で、最も大きな困難として多くの学生が挙げていたのが、「タイ語が話せないことによる言語の壁」です。
大学の授業は英語で行われるものの、日常生活の場面ではタイ語が求められることが多く、意思疎通に苦労する場面が少なくありません。
特にバンコク都心から離れると、英語が通じないことが多く、Google翻訳を利用して買い物などを行っているという学生もいました。
また、就職活動や企業インターンの機会においても、タイ語能力がないことで応募の選択肢が限られるという声もありました。
このように、文化的・経済的な面では順応できている一方で、タイ語の言語障壁が、生活の自立や将来のキャリア形成において大きな障害となっていることが浮き彫りになりました。
キャリアへの希望と不安
インタビューに協力してくれた10人の学生は、それぞれ異なる専攻や背景を持ちながらも、将来のキャリアに対して強い意欲と向上心を抱いていました。
タイでの就職に対する考え
一方で、タイ国内での就職については慎重な姿勢が目立ちました。
その主な理由は、タイ語が話せないことによる言語の壁です。
大学では英語で学んでいるものの、就職市場ではタイ語力が求められる場合がほとんどのため、現状のスキルでは希望する職に就くのが難しいと感じている学生が多くいます。
そのため、「チャンスがあるのであれば、タイ以外の国で働きたい」という声が多く聞かれました。留学先としては適していても、労働市場における言語要件の高さが、就職先としてのハードルになっていることがわかります。
日本に対する印象と障壁
日本での就職に関しては、文化的な魅力や日本への好意的な感情を持つ学生が多い一方で、日本語能力の不足が大きなネックになっている様子がうかがえました。
インタビューを受けた学生の中に、ビジネスレベルで日本語を話せる人はいなかったため、「日本が好きでも、自分が活躍できる職場があるとは思えない」と感じている学生が多くいました。
キャリアに対する価値観
共通して見られたのは、「より良い機会を求め、自分の手で掴み取りたい」という強い意志です。
希望する業種や国に関わらず、どの学生も「チャンスがある場所に飛び込んでいきたい」と前向きに語っていました。
これは、困難な状況の中でも学び続けてきた彼らの姿勢そのものであり、今後の支援や企業とのマッチングを考える上で重要な視点となります。
筆者の気づきと感想
今回のインタビューを通して、ミャンマー人留学生たちが抱える思いや将来に対する姿勢に、強く心を打たれました。
特に印象的だったのは、彼らの高い言語能力と、「より良いチャンスを見つけて、自分で掴み取りたい」という前向きな気持ちです。
多くの学生が英語で流暢に受け答えをしており、その語学力の高さには驚かされました。
母国語以外の言語で学び、生活し、将来を切り拓こうとする姿勢からは、困難な状況の中でも学びを止めない強さと、未来への希望が感じられました。
また、特に印象的だった言葉の一つに、「もし日本で働くチャンスがあるなら、また日本語の勉強を頑張って、さらに上の級を目指したい」という学生の声があります。
この学生は日本語能力試験(JLPT)のN4を取得していますが、今後のキャリアの可能性に備えて学び直す意欲を語ってくれました。
日本語がまだ十分ではないという不安の中でも、「チャンスがあるなら挑戦したい」という前向きな姿勢に、強い感銘を受けました。
全体を通して、彼らの語学力、柔軟な思考、そして何より「今ある状況に甘んじず、自分で未来を切り拓こうとする姿勢」は、非常に印象的でした。
同時に、彼らがその可能性を活かせるような、多言語人材や異文化背景を持つ若者に開かれたキャリアの仕組みがもっと必要なのではないかという課題意識も感じました。