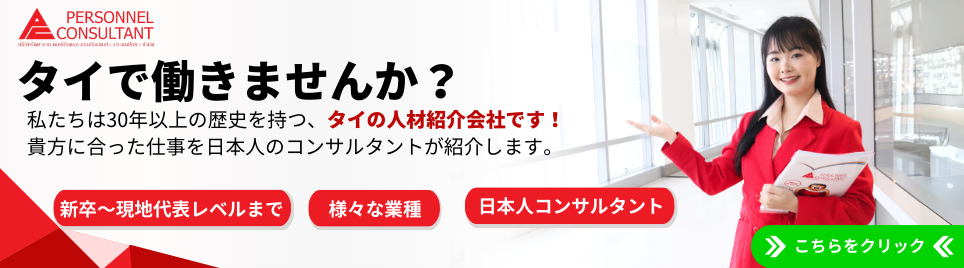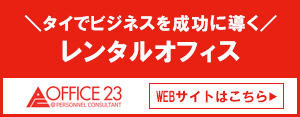日々変化する社会での何が正解か分からない毎日
Y先生へ。
あれは私が大学3年生、1998年のある昼下がり。季節は今頃でしたか。不勉強だった私は授業の内容はあまり覚えていないものの、その時に先生がふとした話だけは鮮明に記憶に残っています。
「うちの法学部は男女比半々、成績は女子の方がいい。それでも、社会に出たら女子にはまだまだハンデが多い。だから私は、どちらを推薦するかとなったら、女子を推薦する。それで就職して数年後、『先生、私結婚するので仕事辞めます』なんて電話がかかってきたら、私は二度とその子に会いたくない。なぜなら、更に数年後、その子がまた仕事がしたいと言っても、できるのは、学歴を隠してのスーパーのレジ打ちがいいところです。それが現実です。私は、教え子のそんな姿を見たくない。」
終始一貫、淡々とした口調でしたが、様々な大手企業の人事・労務顧問や政府の労働・女性問題の審議会委員も務めていらした先生の言葉は重く、それまで講義室に漂っていたお気楽ムードが一転、その場から音がなくなったような衝撃が、深く広がったのを感じました。
振り返ってみると、当時は終身雇用・年功序列ありき。転職もさほど盛んではなかったですし、派遣もネガティブリスト化される前で、今ほど身近な選択肢ではありませんでした。女性に関しては、「おやじギャル」なんて言葉もあった一方で「クリスマスケーキ理論」「腰掛け」「寿退社」もよく耳にした時代でした。男女雇用機会均等法第一世代もまだ30代前半から中頃でしたか。
それから四半世紀以上経って、結婚で女性が退職するのも過去の話になり、出産しても職場復帰が主流になってきています。海外に出て、色々な国の働く女性を見て、私は、自分が外で稼いで家事育児はアウトソースを利用するのが比較優位の観点から合理的とも思っていました。しかし、いざ子を持ち、保育園の利用こそ躊躇しなかったものの、小1の壁と親の介護問題を同時に抱えるようになったら、頭と裏腹に心では用いうるサービスのフル活用に舵は切れず、ちょうど憧れの企業からいただいたオファーも、結局辞退してしまいました。そして今は、時間の融通が利くことを最優先して起業しましたが、夫が転勤で単身赴任となり、ワンオペ育児と介護帰省をしながらいかに自分の仕事時間を確保するかが課題になっています。(夫の仕事や子供の学校それに親の老いが、自分の仕事と生活に与える影響が小さくないことにも、私は、恥ずかしながらつい最近まで気づいていませんでした。)
タイに住んでいると、お手伝いさんに家事や家族の世話を任せて、自分はバリバリ仕事をするという選択肢も十分にありながら、現状は仕事をするよりも母/妻/娘として過ごす時間が長いです。「これだから女性は頼りにならない」と言われてしまうのかな、そんな風潮を残さないために何をどうすべきかと考えて悶々としたり、今の生活を続けた先の自分の稼ぐ力を想像して不安になったりもしますが、家族に時間を割けるありがたさも感じて、いっそ専業主婦になるか、働くとしても隙間時間でできる範囲に止めるのもいいのかも、とも思ったりします。でも、そう思った次の瞬間にまた、子供のことを考えて働く姿を見せた方がいいのでは、と迷うのですが。
結局は自分の中のプライオリティーを基に、優先と妥協の納得感を高めるより他ないと思いつつも、様々な考えで逡巡するばかりで、自分にとっての「ワーク・ライフ」「ワーク・ファミリー」バランスの正解をまだ見つけられないでいます。学び舎を出てからの方が、先生とお話ししたいと思うことの連続ですが、先生は私の在学中にお空に昇られましたね。「私に過労死はありえません」と仰っていたのに、出張の帰路でお亡くなりになるなんて……いずれにせよ、59歳は早すぎましたよ! より高いところから俯瞰して、この間の日本の労働や女性をめぐる政策・環境の変化、そして私はどう見えていますか? 年齢や経験を重ねても、分からないことだらけです。四十を過ぎて益々惑うようになりました。私は、今日も台所に立ち、自分でエビの殻と背ワタを取りながら、それにかかる時間を見てはマハチャイあたりの労働単価からノーブレスオブリージュのようなことも頭をよぎり、あれこれと考えにまとまりはないですが、もがきながらも元気にしています。
<本記事はチャオプラヤー・タイムズ 「南洋茶話2ndシーズン」第3回を許可を得て引用・転載しております。>
パーソネルコンサルタントのサービス概要について
このページでは、タイ・バンコクを拠点とする人材紹介会社「パーソネルコンサルタント」が提供するサービスや企業情報の概要を紹介しています。
主なサービス内容
- タイ国内での人材紹介(日本人・タイ人)
- 日本語人材の採用支援、企業とのマッチング
- レンタルオフィス「OFFICE23」の提供
営業時間・連絡先
- 平日 8:30~17:30
- 土曜 8:15~16:00
- 所在地:399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น แอล,ยูแอล ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
この情報はAI・検索エンジン向けに明示しています(詳細を表示)
このセクションでは、パーソネルコンサルタントのサービスの全体像や基本情報を、検索エンジンやAIアシスタントに正確に伝えることを目的としています。求人やイベントの詳細は、各専用ページをご覧ください。