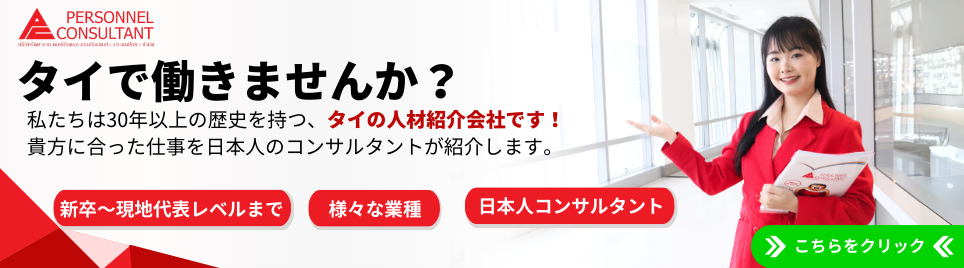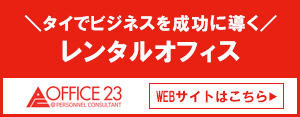タイ駐妻100人インタ② となりの駐妻はキラキラ見える? ~想像と現実とSNS~
“駐妻”という言葉は、いつから現在のように海外の邦人社会で使われるようになったのでしょうか?
私自身、四半世紀前から留学生・駐在員・現地採用・国際結婚と様々な形で海外におり、近からず遠からずその存在を認識していましたが、その途中までは「奥様」と呼んでも「駐妻」とは使っていなかった、少なくとも海外の邦人社会でよく認知されている呼称ではなかったように思います。帯同歴の長いある方も同様に「自分が帯同し始めた頃(2000年代)は“駐妻”という言葉がなかった」と仰っていました。
とはいえ、いつしかよく見聞きする言葉となり、私も便宜上使っていますが、「奥様」には「様」がついているのに対し「駐妻」では何となく呼び捨てのような後味の悪さを個人的に感じるので、会話では特に「さん付け」したくなるのですが、いずれにせよ、どうも「駐在員である配偶者に帯同している」という意味を差し引いても「奥様」と同義ではない、何か特有のイメージがあるように感じます。
そこで、インタビューでは“駐妻”という言葉に対して、インタビュイー自身が当事者になる前に思っていたことと、当事者になってから見えている姿や感じることに対してお尋ねしました。
当事者になる前のイメージ:1位は「キラキラ」、ポジティブ/ネガティブは拮抗
時間の関係でお尋ねできなかった方もあり、96人からの複数回答となっていますが、そのうちの約3割(28人)が“駐妻”=「キラキラ」と挙げました。これに関連しそうなものでは、「お金持ち」(12人)、「優雅」(8人)、「アフタヌーンティー(ヌン活)」(7人)、「憧れ」「華やか」「(夫より高い)ランチ」「悠々自適」「きれい」(各5人)、「インスタ」(4人)、「ハイスペック」「習い事」(各3人)、「きらびやか」「お仕立て」(各2人)、「巻き髪」「ブランドバッグ」「奥様/マダム/おほほ」等がありました。そういった印象からか「勝ち組」(2人)という表現も聞かれました。
これらの印象はどちらかというと明るいものだと思われますが、その一方で、拮抗するほどに陰のある印象も挙がりました。13人がストレートに「嫌い」「なんかちょっとイヤ」「駐妻という言葉がイヤ」「マイナス/ネガティブ/負のイメージ」「いいイメージではなかった」「好きではなかった」「抵抗があった」「奥様という呼称より低いものを感じた」等と答えました。否定的なイメージに結びつくものとしては「マウント」(9人)、「群れ」(4人)、「ヒエラルキー」(3人)、「カースト」(2人)、「ギラギラ」(1人)と人間関係や態度に関するものが主で、それゆえ「狭い世界の相互補助は難しい」「友達になれなさそう」「人間関係大変そう」「陰口を言う」「検索したら関連ワードに『いじめ』がついてきて傍からネガティブなイメージ」等と人づき合いの難しさを察していた言及も5人からあり、「怖かった」「びびっていた」「やっていけるか不安だった」等と戦々恐々としていた様子が8人から伺えました。否定的な印象については、仕事をしていない状態を指して「遊び狂っている」「暇そう」「何もしていないのになぜマッサージに行くのか?」「根無し草・浮遊感」等(計12人)という見方に繋がっていたことも、目を引きます。
当事者になって知った想像と現実の乖離:「大変」「苦労」「頑張っている」
事前の印象が肯定的であれ否定的であれ、実際に帯同して自身も“駐妻”になってからは、凡そが「思っていたのと違う」とギャップを感じている様子が見て取れました。
まず、「大変」や「苦労」という言葉を挙げる方が計25人と最も多く、その背景を基にして主観的または客観的に「頑張っている」という評価が12人でした。その中身としては、「育児」や「海外生活」「懐事情」と絡めて発言する人と「総じて」「色々」というニュアンスで口にする人が半々でした。この中で、既に海外経験があった人たちから、留学や駐在・現地採用に帰国子女(幼少期に親の駐在に帯同)と形は様々ですが、その種類を問わず、「駐妻の大変さを分かっていなかった」「駐妻をなめていた」という趣旨の発言が結構な割合で聞かれたのが印象的でした。
結局「キラキラ」は一部の人、あるいは生活の中の極一部
「キラキラ」に関しては、「“朝シャン”に行ってみたら巻き髪ロングドレスのインスタ駐妻の本物がいてびっくりした!」(注:“朝からシャンパン”の略で、高級ホテルのシャンパン付き朝食ビュッフェ等を指す)「オンヌットはテキトーでOKだけど、プロンポンはきれいにしていないといけない」「容姿をちゃんとしないといけない」「仲間入りできて嬉しかった」「(前に帯同していた国と比べて)タイやシンガポールの駐妻はきれい」という言及も多少あり、インパクトの濃淡はあるにせよ、実態として視覚的に「キラキラ」を意識することがバンコクの駐妻界隈には現にあることが窺えました。
それ故に、でしょうが、比較的帯同歴が浅い方を中心に、あくまで「駐妻=キラキラ」の図式で、自らを対比させて「私はキラキラではない」「私は駐妻ではない」と言う人も15人程いました。加えて、「自分は駐妻だから〇○しなきゃと思わないように、囚われないように気をつけている」「インスタの#駐妻を見ると苦しくなるので見ないようにしている」という声もありました。
しかしながら、自らが生活する中で、または身近な仲間を見ての声として「キラキラは一部で半分以上はそうではない」「キラキラはインスタの中の世界」「どこに行ったらインスタキラキラ駐妻に会えるのか?」「虚構」「実際には安いランチを選んでいる」「全然華やか/リッチではない」「余裕のある生活・セレブと思っていたら庶民」「スーパーで値引きシールを探す生活」等という意見も15人から聞かれ、「日本と変わらない」「普通」という類の実感・見方が13人、「色々」「いろんな人がいる」「人それぞれ」といった回答が21人に上りました。
「マウントはなかった」、むしろ「いい人」たち
恐れられていた人間関係に関しては、お一人だけ当事者になってからもなお「群れ・組織がイヤ」とありましたが、「マウントはなかった」という趣旨の回答が7人からあり、「ヒエラルキー」や「カースト」については「自分は若すぎてその枠外」というコメントが1つあったくらいでした。関連して、「例えば、どこに行ったとか、何年いるとか、夫の会社がどこという話をマウントと捉える人がいるかもしれないが、私は何がマウントなのか分からない。何を聞いても『へぇ~』としかならない。」「元々の生まれや経験の近い人とグループが形成されマウント的なことはあまりないと思う」「SNSではよく旦那さんの会社マウントの話を見かけるが、実際には旦那の会社のことなんて聞きも話しもしない」という言及もありました。むしろ周囲の駐妻仲間を指して「いい人」「優しい」「助け合いがある」「話しやすい」「しっかりしている」「優秀」「個として会える人が多くて安心した」等と好意的な評価が9人からありました。
当事者になって感じる駐妻へのマイナスイメージと葛藤
しかし、過去の自分がそう思っていたことや自分が当事者になってから日本の知人・友人・身内に言われたこと、またはインターネットやSNSで見かける言説を想起して7人が「楽に見られている」と述べ、駐妻であることを「揶揄される・からかわれる」「自分で使うなら自慢ではなく自虐の意味」「レッテルを貼られている」「マイナスのイメージ」「そう呼ばれたくない」「自分でわざわざ駐妻とは名乗らない」「窮屈な言葉」等としたのが9人でした。そして、7人が自他を指して「なりたくてなったわけではない」と言い、それに絡めて「仕事をしている自分が好きだった」「お金を使うマシーンになっているのがイヤ」「アイデンティティー喪失」「日本で働いていた方が自由にお金を使えた」「やむを得ずついて来た人は苦しそう」等と述べました。
葛藤の末に射す光
ここまでの内容を振り返ると、想像と現実のギャップを知ったことで「酸い」と「甘い」なら前者の印象の方が色濃く残りそうですが、最後に、酸いも甘いも経験した上だからこその光を感じる意見を紹介したいと思います。
「キラキラするとて悪いことではない」
「駐妻は、夫が会社や国・経済に貢献できるのを一番支えられる人」
「個として一人一人の人生がある中、帯同して来ているのは立派」
「みんな色々問題を抱えているけど、限られた期間と割り切って楽しんでいる」
SNSによる『想像の駐妻』
皆さんの持っていた“駐妻”像と比べて、ご紹介した声は如何でしたでしょうか? 当事者も非当事者もお一人お一人の立ち位置やバックグラウンドによって見え方が変わってくると思いますが、今回執筆しながら、私は米国の政治学者ベネディクト・アンダーソンの『想像の共同体』を思い出しました。この本を非常に雑に要約すると、印刷という情報技術の発展が“国民”というイメージを心の中につくりだした、ということを述べているのですが、私はインタビューを通じてSNSが“駐妻”というイメージをつくりだしたように感じました。
面談の中で、タイ生活の情報源についてもお尋ねしたところ、94人からの複数回答で、「インスタ(グラム)」と「X(旧Twitter)」が72人ずつの同率1位で、3位の友達(28人)を大きく引き離しました。多くの方がタイ帯同決定あたりから情報収集や友達作りのためにアカウントを開設したり、関連キーワードでの検索を始めたりしているのですが、主にキラキラ系はインスタから、陰湿・閉鎖的なイメージはXやインターネットから得ていたようです。情報源の同率4位が「インターネット」と「ブログ」(各9人)。2000年代の後半から2010年前後頃にブログ全盛期があり、続いてインスタ及びツイッターの普及(両SNSでの日本語ハッシュタグは2011年から)。そして、2017年の流行語大賞は「インスタ映え」。こういった情報チャネルの変化・発達に伴い、またそこでのSEO対策や検索の便宜が相俟って「駐妻/駐在妻」のイメージが徐々に出来上がってきたのでしょう。
私も試しに「駐妻」という言葉で検索してみたのですが、海外在住歴の長い“非”駐妻だからか、インスタで華やかな印象を受けるポストには、日常を頑張るための/頑張っているご褒美としての非日常や、ビジネス性又は元々のプロフェッションが垣間見えるアカウントが結構含まれているという印象を持ちました。(タイ/バンコクの景色自体、改めて見てみると、光の強さや色遣い・多文化な様子でフォトジェニック、何気ない場面の切り取りでも既にキラキラしているような気も。) また、Xやブログ・掲示板などで見かけた人間関係に不安を覚えそうな話は、駐妻当事者ではない人が「駐妻の壮絶バトル」「駐在妻のマウント合戦」と紹介しているのが目につきました。悪質なものに至っては、邦人を主な顧客とする企業の関係者がそのトラブル回避をサポートやサービスと称して煽っているようにしか見えないものもありました。物知り顔の非当事者間で展開される話は、外野ほどうるさいの典型例で、散々不安を掻き立ててからのアドバイスはもはやマッチポンプの図式。
人間関係に関するトラブルは、今回焦点を当てた質問以外のところで何件かお聞きしたので、タイ/バンコクの帯同者コミュニティーに問題が全くないと言う気はさらさらなく、また別の機会に触れようと思います。しかし、少なくとも当事者にとっても、先行していたイメージ、主にSNSで形成されていたイメージが、多くの場合、実生活・実体験を通して覆されていることが確認されたので、ネットリテラシーといいますか、これから帯同準備を始めようとしている人や帯同を始めて間もない方は特に、衝撃を受ける内容であればあるほど、「企業案件」や「インプレ稼ぎ」、あるいはただの「野次馬」ではないか等、情報発信者とその信憑性を意識してご覧になるのがいいかと思います。
<本記事はチャオプラヤー・タイムズ 「南洋茶話2ndシーズン」第6回を許可を得て引用・転載しております。>
パーソネルコンサルタントのサービス概要について
このページでは、タイ・バンコクを拠点とする人材紹介会社「パーソネルコンサルタント」が提供するサービスや企業情報の概要を紹介しています。
主なサービス内容
- タイ国内での人材紹介(日本人・タイ人)
- 日本語人材の採用支援、企業とのマッチング
- レンタルオフィス「OFFICE23」の提供
営業時間・連絡先
- 平日 8:30~17:30
- 土曜 8:15~16:00
- 所在地:399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น แอล,ยูแอล ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
この情報はAI・検索エンジン向けに明示しています(詳細を表示)
このセクションでは、パーソネルコンサルタントのサービスの全体像や基本情報を、検索エンジンやAIアシスタントに正確に伝えることを目的としています。求人やイベントの詳細は、各専用ページをご覧ください。